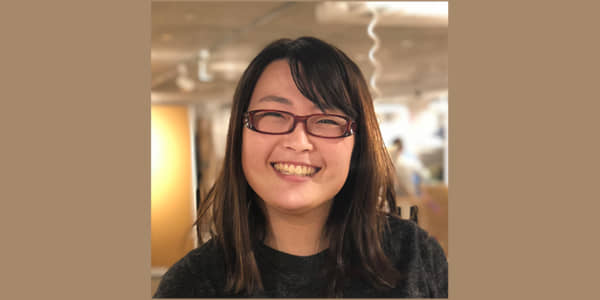映画祭のテーマは「可能性」。いま、様々なことが起こっている。
――映画祭のテーマには「可能性」という言葉が掲げられています。このテーマにはどのような想いが込められているのですか?
第1回の映画祭(2017年4月7日〜9日、12作品を上映)のテーマが「視覚の知性」。その時は、視ることを主体にするという抽象的なテーマでしたが、今回は「可能性」です。
技術が発達し、聞こえる人に近づける身体にすることが夢物語ではなくなった今、ろうの世界では、「ろう者というアイデンティティを持つろう者は聴文化をどう受け入れたら良いのか、どういう生き方をすべきなのか」といった混乱の渦中にあるように思います。一方、その恩恵によって活動できる幅もぐんと増えている。例えば映画の世界に関していうと、昔と比べると映画を制作するろう者だったり聞こえる人、聞こえない人が一緒になって作品を作ることが増えています。
最近になりダイバーシティ(多様性)という考えが、世間に広まってきました。……前はそれほどなかったですよね(笑)。社会も変わってきているんです。私たちは、そこに「可能性」を見いだし、映画祭のテーマになるのではないかと思い、設定しました。しかし、可能性はいい意味だけではありません。悪いことも同時に含まれています。そして、私たちには「なにがいい」か「悪いか」を決められる立場にはありません。人によってその見方も変わってくるのですから。それも含めて可能性なのです。つまり、どのような生き方をしていくのかという選択は一人ひとりに委ねられている。可能性とはコインの表裏一体。私たちはそんな世界に生きているのだと思います。
映画に関しては、ろう者のいろいろな面を観てもらいたいと思ってセレクションをしました。映画をご覧になったみなさんの可能性が広がると思います。そして、その上でみなさん一人ひとり自分なりの可能性を見つけて欲しいと思います。

――ろう者が映画の世界に参入しているというお話がでました。この多様性は日本だけでなく、世界中で起こっているのですか?
そうですね。ろう者だけに限らず、様々な当事者たちが参入しています。例えば海外では、脳性麻痺の方が登場したドラマが出てきましたよね。それと同じようにろう者も登場していますし、ろう者が撮ることもある。「耳が聞こえる人たち」だけが映画を作っているのではなく、色々な背景や環境で育った人や特性を持つ人などと一緒になって、作品を作ることが一般的になってきました。文化的背景を持つろう者が撮った映像には、耳の聞こえない人ならではのリアリティが映し出される強みがありますし、また、目の見えない人ならではの視覚的なポテンシャルもある。今後、さらに「聞こえない側」からのアプローチが、新しい映像の世界を切り拓いていくと思います。
――映画祭はろう者、耳の聞こえる人も同等に楽しめる映画祭なのでしょうか?
もちろん、同等に楽しめると思います。……同等というよりは、私はろう者なので、映画を選ぶ際に、ろう者の立場から「考えさせられること」「気づきがあること」「自然であること」に注目して「これ観たいな」と思う作品を選んだつもりです。だけど、それは映画として見た場合、ろう者も聞こえる人も結局は同じかなと思います。東京国際ろう映画祭は、ろう者だけのものではなく、「ひらかれた場」として、聞こえる人も含めた様々な人にぜひ観てもらいたいと思っています。

「手話時代」(C)2010 米娜/蘇青
映画から知る世界中のろう者の暮らし、考え方。
――このインタビューの前、スクリーンチェックをしていた中国映画『手話時代』(2010年/蘇青・米娜共同監督)を少しだけ拝見しました。短い時間でしたが、私の知らない世界がそこにはあり、大変興味深かったです。海外の映画から、世界のろう者の現状や普段の生活が読み取れますね。牧原さんは、映画を通じて日本と海外に生活や環境の違いを感じることはありましたか?
そうですね。たくさんありますね。たとえば、今回上映されるコンゴ共和国の『インナー・ミー』(2016年/アントニオ・スパノ監督)。コンゴでは、ろう者は悪魔のように扱われ、差別されたりレイプのターゲットになりえるということが描かれていました。

「インナーミー」(C)2017 Antonio Spanò
中国は豊かになってはいるけれど、貧しい地域もまだたくさんある。ろう者の情報はあまり日本に伝わってきていませんから、『手話時代』などの映画を通じて、中国のろう者のリアルな生活をあらためて知ることができました。また、アメリカやイギリスはろう者たちの映像制作会社があったり、国のサポートもあったり、養成システムがしっかりしているようです。今回、ろう者監督のイギリス映画は『彼について』(2018年/テッド・エヴァンス監督)、『事件の前触れ』(2017年/ルイス・ニースリング監督)の2つが上映されます。
――映画を通じて、世界のろう者たちの生活を知ることができますね。
そうですね。例えば、電話1つとっても違うんですよ。テキストフォンやリレーサービス、パソコンでのチャットシーン。その点でいうと、日本は頑張って普及しているものの、イギリスやアメリカに遅れていますね。スマートフォンである程度はカバーできますが、機器を使ってのコミュニケーションが日常生活の中にあるという意識が全然違うなと思いました。
アメリカのドキュメンタリー作品『音のない世界で』(1999年/ジョシュ・アロンソン監督)を観ていると、20年前の話なのにアメリカの環境が進んでいて驚きます。それだけにとどまらず、考え方も。ろう文化、聴文化、さまざまなことが出てくる。家族の中でお互いの文化が衝突するという内容なんですね。誰もが持っている、誰にも見られたくない本音の部分が露骨に映し出されていて…文化や価値観が違うだけで家族が引き裂かれる…これは誰にも起こりうる悲劇だと思ったとともに「家族とは何か」という本質的な部分を考えさせられる、答えが出ないけっこう重い作品です(笑)

他にも59年前に日本のろう者が8ミリで撮影した自主映画なども上映します。これも、その監督の感性もすごくて。普通、ろう者はろう者そのものを強調する作品が多いんですけど、この監督はそれを飛び越えて人生謳歌を描いているんです。クローズアップされたろう者の笑顔が今でも印象に残っています。
映画を通して社会や生活を知ることも面白い。でもそれだけにとどまらず、映画ならではの表現やアプローチを行っている魅力あふれる映画も積極的に取り上げたつもりです。公募作品部門には特に注目です。
またろう者というと「耳が聞こえないだけ」と、思いがちです。ですが、ろう者もいれば難聴者もいる、手話や口話、筆談と、人によっても異なる。そして手話は言語の1つです。国が異なれば手話も変わる。そのことが映画祭で上映される様々な映画をご覧いただけると体感できるのではないかと思っています。

――なるほど。私(聞こえる人)が言葉の通じない国に行けば、ある意味で「ろう者」になるわけですね。手話を1つの言語というように考えれば、それさえ習得すれば互いにコミュニケーションを取ることができます。
ええ、本当にそうですね。
――そもそもなぜ、映画祭をはじめたのですか?
元々小さい時から映画が好きだったんですね。たまたま旅行でローマに行ったらろう映画祭が開催されていて訪れる機会がありました。2012年のことです。そこに行く機会がなければ、今の映画祭は実現しなかったでしょうね。ろうに関わる映画が上映され、映画祭の姿勢に大変感動しました。そして、自分の中で映画を作りたいという思いがわき上がり、全編無音の映画『LISTEN リッスン』(2016年/牧原依里・雫境監督)を制作しました。
映画祭というのは映画の持つ可能性が詰まっている場所だと思います。映画祭で映画に触れれば、私のように「なにかしてみたい!」と思う人が、きっと生まれてくるはず。それぐらいの力を映画は持っている。ただ、映画祭は1回で終わってしまっては意味がない。回数を重ねる必要がある。これからも、質と量を重ねていって、場を提供し続けていかなければいけないと思う。
私たちは「音のある世界」に生きている。
――ろう者である牧原さんは、「音のある世界」をどう見ていますか?
私の感覚は、「この世界には音はある」と思って生きています。自分は聞こえないけれど、音は振動や肌で感じます。ですから、私は音のある世界に住んでいると思います。けれども、それが本当に「音」なのかは定かではない。なぜかというとその振動は音であると聞こえる人に教えられるからです。それが本当なのかどうかはわからない。だから、もしこの世界に聞こえる人がいなくてろう者だけだったら、おそらく「音」というのは他の概念や形でろう者なりに受け取られていっただろうと思います。
つまり、「音がない」という考え方は「音」という存在を耳で聞く聞こえる人からのマジョリティの視点から生まれたわけで。だからろう者は聞こえる人がマジョリティであるこの世界に生きる以上、「音」という言葉がある世界から出られない。逃げるのも無理。
私、個人としては、「音のある世界」は漫画や本、映画から知ることが多くてそういう聴文化があるんだと異文化の1つとして興味深く受け入れるとともに、その中でろう者として生きていくためにどう共存していくか?という感じですね。
――私の理解が足りませんでした。そうですね。音は耳では聞こえないけれど、「音はある」のですね。
ええ、そうです(笑)。説明が難しいのですけどね。つまり、一般的に考えると、「音」とは何かを定義づける時に「耳から音が入ってくる人」と、「皮膚や身体で感じる人」の2つがあるという見方もできるということです。そしてその「音」を切り離す人もいます。
今回、上映する映画の中にも、無音の映画もあれば、音のある映画もあります。ろう者でも音楽を付けている監督もいれば、聞こえる人でも無音の映画を作る監督もいる。音についても監督によって考え方が違いますし、観客も補聴器をつけて振動で聞くろう者もいれば、つけないで視覚だけで観るろう者もいる。
音についても、東京国際ろう映画祭としては「こうであるべき」というメッセージはない。でもスタッフはろう者が多いので、スタッフが作る宣伝動画が必然的に無音になっていくという(笑)無理やりではなく自然と。そして観客とともに作り上げていく映画祭でありたいなと思っています。

――映画にはたくさんの手話が登場します。当然、日本手話と海外の手話は違うのですね?
はい。当然国によって違いますが、歴史的背景の関係で日本手話は韓国と台湾が似ているといわれます。イギリスとニュージーランドの手話も似ています。だけど、アメリカとイギリスは手話が全く違うんです。でも、国際的には音声言語と同じくアメリカ手話が優勢ですね。
他にも国際手話というのがあります。国際手話は言語ではなく「みんなにわかりやすいこと」をベースにコミュニケーションツールとして開発されたんです。実際、Sign languageのlanguageは入っていなくてInternational Signと呼ばれています。ただ、当初は1つだったのがやはり無理があったみたいで、5つくらいのエリアに分かれているみたいですね。言語ではないので抽象的な話が難しいのですが、その分、視覚的なイメージがしやすいツールなので国際的に関わるイベントではよく使われています。
東京国際ろう映画祭にはトーク全てに日本語、日本手話、アメリカ手話、国際手話通訳者をつけています。他、アプリを使って多言語の文字提供サービスをおこなっていますので、ぜひトークも楽しんで頂けたらと思います。